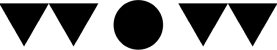わかりやすい陶器と磁器の違いや見分け方・電子レンジ使用の
注意点
普段わたしたちが何気なく使っている陶器や磁器(まとめて陶磁器ともいう)ですが、「違いや見分け方までは分からない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、見た目や触感による見分け方、原料の違い、電子レンジを使うときの注意点を分かりやすく解説します。
陶器と磁器の
違いと見分け方
陶器と磁器の違う点は、大きく分けて以下の3つです。
・外観や触感、強度
・焼く温度と原料
・歴史
それぞれ詳しく見ていきましょう。
陶器と磁器の違いその1:
外観と触感、強度
陶器と磁器は、下の表のように外観や触感からでも見分けられ、強度にも違いがあります。
| 陶器 | 磁器 | |
| 触感の違い | ・ザラっとしている ・軽くはじくと、ゴンという鈍い音がする |
・ツルッとしている ・軽くはじくと、キーンという金属音のような高い音がする |
| 外観の違い | 素地:おもに茶色やグレー、褐色、アイボリーなどの有色 釉薬:透明や有色、さまざまな色がある。かけるものと、かけない焼締めとがある厚さ:厚手で、光にかざしても透けない |
素地:白
釉薬:透明か青色
|
| 強度の違い | ・重くて割れやすい | ・軽くて固い
|
陶器と磁器のうつわは、触感や素地(きじ=うつわを焼く前の成形された状態のもの)の色が違います。
陶磁器の表面に有色の釉薬(ゆうやく=陶磁器の仕上げにかけるガラス質の膜)が塗られている場合、素地の色が分かりません。
その場合は、釉薬のかかっていない*高台や、高台の脇の部分で色を見るようにしましょう。
*高台とは:茶碗やお皿の底を支えている、輪の形の台の部分

また磁器は高温で焼かれるときに、磁土に含まれるケイ素と釉薬がガラス化するのでツルッとした触感になるのが特徴です。

陶器と磁器の違いその2:
焼く温度と原料
製造工程での大きな違いは、原料と焼くときの温度です。
| 陶器 | 磁器 | |
| 原料の違い | 陶土(おもに粘土) | 陶石(けい石や長石など) |
| 焼成温度の違い | 1,000〜1,300度 | 1,300〜1,400度 |
| 吸水性の違い | ある | ない |
どちらも釉薬をかけてから焼きますが、高温で焼く磁器のほうが固く焼き固まり、吸水性がないという特徴があります。
陶器と磁器の違いその3:
歴史
陶器の製作は古く縄文時代から日本でおこなわれていました。
対して磁器は江戸時代に本格的に製作がはじまったので、歴史が浅いといえます。詳しくは、以下の表の通りです。
| 陶器 | 磁器 | |
| 起源の違い | 約1万2000年前 縄文土器からすでに製陶がはじまっていた |
11世紀に留学僧が日本に中国の磁器を持ち込んだといわれている |
| 発展した時期の違い | 5世紀ごろ 弥生時代に中国や朝鮮半島からろくろや窯の技術が伝わり高温焼成が可能になった |
1610年代(江戸時代初期) 肥前(佐賀県)有田で初めて磁器が焼成された |
陶器と磁器の電子レンジ
使用上の注意
磁器は電子レンジの使用ができます。
ただし、金や銀の装飾があるものはレンジ内で放電が起こり火花が出る危険があるのでレンジに入れてはいけません。
色絵などの塗料もはがれる可能性があるので、ご注意ください。
では、陶器の場合はどうでしょうか?
基本的に、陶器は電子レンジの使用には向いていません。
なぜなら急激な温度上昇によりやきもの内部の水分が膨張し、割れるリスクがあるからです。
陶器は粘土が原料なので、細かい穴から煮汁や水道水を吸収します。そうして内部の気泡にたまった水分が、急激な温度変化で膨張し、張り裂けることがあるのです。
例外として、固く焼きしまった陶器は電子レンジが使用できます。
その場合でも、冷めた陶器を急にレンジに入れたり、長時間あたためたりするのは避けましょう。
セラミックや白磁、ボーンチャイナと
陶器・磁器の違い
次にセラミックや白磁、ボーンチャイナなど、陶器や磁器とどう違うのか分かりづらい用語について、それぞれご説明します。
セラミック:
陶器や磁器はセラミックの一種です。
陶磁器をはじめ、ガラス、セメント、ファインセラミックスなど高温で粉や粘土を焼き固めたものをまとめてセラミックといいます。
最近はセラミックというと、人工原料を加えて半導体や歯の詰め物などに使うファインセラミックスを指す傾向にあるため、違うものだと認識されがちです。
一般的に、食器を指していうセラミックは、陶磁器のことだと考えてよいでしょう。
白磁:
模様がなく真っ白な磁器。純度の高い磁土に、不純物が少ない釉薬をかけて焼きます。
磁土と釉薬に鉄分が少ないほど真っ白になるのが特徴です。
基本的に、白磁には文様を描きません。
ボーンチャイナ:
粘土や長石、石英に動物の骨粉を加えて焼いた磁器の一種。
ボーンは「骨」、チャイナは「磁器」の意味の英語から名付けられた名称です。
骨を多く含んだ素地を焼くので、白磁のおよそ2倍もの強度があるとされています。
軽くて薄く、色は白磁のような真っ白ではなく少し暖色系の白です。
ほかにも「瀬戸物(せともの)」という言葉がありますが、こちらは陶器と磁器の総称です。
日本陶器の起源とされている愛知県の瀬戸焼に由来しています。
陶器と磁器の使い分けと
お手入れ方法
陶器と磁器のお手入れ方法を、
・購入後
・使う直前
・使った後
の3つの段階に分けてご説明します。
購入したあとの
お手入れ
陶器と磁器共通:高台をなめらかに磨きます。
触ってみてザラザラしていたらサンドペーパーや砥石で磨くか、高台同士をこすり合わせるのもよいでしょう。
ただし、こすり過ぎて変形しないようご注意ください。
陶器:半日ほど水に浸すか、米の研ぎ汁に20分ほどつけます。
陶器の表面には、目では見えない穴が無数にあり吸水性があります。水に浸すことで、目が詰まり油や調味料を染みにくくする目的です。
磁器:購入後、そのまま使えます。
使う直前の
お手入れ
陶器:使う直前にも湯水に一度くぐらせます。
料理の水分によるシミを防ぐのが目的です。
とくに焼締めの食器は釉薬でコーティングしないので、油分を吸いやすいです。揚げ物などを乗せるときは、ペーパーナプキンなどを敷くとなおよいでしょう。
生ものを乗せる場合は、臭い移りしないようサラダ油を浸したキッチンペーパーなどでひと拭きします。しばらく置いてから洗い流すと臭いが移りにくくておすすめです。
磁器:陶器に比べ水気を通さず汚れがつきにくいので、そのまま使えます。気になる方は、陶器と同じお手入れをするとよいでしょう。
使った後の
お手入れ
陶器・磁器ともに、食器用洗剤で洗えます。
ただし研磨剤が入ったクレンザーは傷の原因になるので、使わないようにしましょう。
焼締めの陶器に限っては、たわしで洗うと表面の凹凸がなめらかになり、おすすめです。
陶器・磁器それぞれの
使い分けかた
結論からいうと、陶器と磁器に厳密な使い分けのきまりはありません。
レストランでも料理とのコーディネートによって、どちらも使われています。
ですので、ここではそれぞれの特徴から向いている使い分け方をお伝えします。
陶器:厚手で熱しにくく、冷めにくいという特徴があるので、熱い汁やお茶を入れるのに最適です。
磁器:水気や油分を通しにくいので、刺し身などの生ものや、揚げ物がおすすめです。
磁器は薄手で熱を伝えやすく、冷めやすいという特徴があります。熱々の汁などを入れると陶器に比べ早く冷めるのがデメリットです。
陶器と磁器それぞれの
有名なやきもの
では最後に、陶器と磁器それぞれの代表的なやきものをご紹介します。
陶器の代表的なやきもの
美濃焼、瀬戸焼、唐津焼、益子焼、信楽焼、萩焼などが有名です。
なかでも人気のある3つについて、簡単にまとめました。
| 産地 | はじまり | 特徴 | |
|---|---|---|---|
| 備前焼 | 岡山県備前地方一帯 | 鎌倉時代 | ・焼締めの代表 ・赤褐色など窯の状態や炎の当たり具合で偶然生まれる色が持ち味 |
| 美濃焼 | 岐阜県の東濃地方一帯 | 室町時代 | ・織部や志野、黄瀬戸など有名な意匠を生み出した ・茶の湯とともに流行した ・江戸末期には磁器作りもさかんに |
| 益子焼 | 栃木県益子町周辺 | 江戸末期 | ・実用性を重視した素朴な【用の美】
・厚手で丈夫 |
磁器の代表的なやきもの
有田焼、伊万里焼、九谷焼、砥部焼、波佐見焼などが有名です。
なかでも人気のある3つについて、簡単にご紹介します。
| 産地 | はじまり | 特徴 | |
|---|---|---|---|
| 有田焼 | 佐賀県の有田町一帯 | 江戸時代初期 | ・日本の磁器の発祥地
・伊万里港から出荷された伊万里焼が有名 |
| 九谷焼 | 石川県加賀市山中温泉九谷町 | 江戸時代(1656年とされている) | ・油絵のような大胆な絵付けが特徴
・諸説あり謎が多く、白磁や青磁を焼いていたともされる |
| 瀬戸焼 | 愛知県瀬戸市 | 鎌倉時代初期 | ・陶磁器を指す「せともの」の由来
・日本で最初に釉薬をほどこした陶器をつくりはじめた ・江戸末期から磁器の生産が陶器をしのぐように |
まとめ
陶器と磁器はそもそも、原料が違います。
見分け方は、軽くたたいたときの音や素地の色を見る方法があります。
普段何気なく使っている陶磁器について、それぞれの特徴やお手入れ方法を知ることで、より愛着を持って長く使えるようになるでしょう。